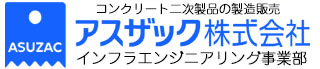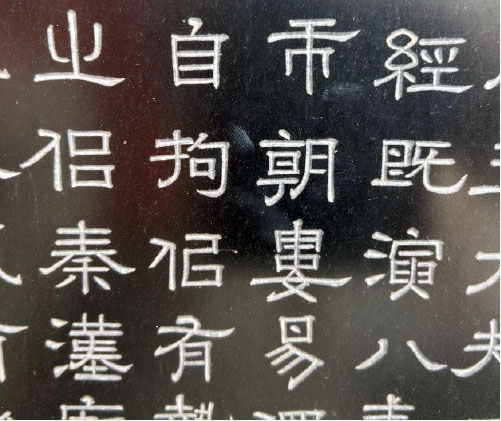白砂青松(はくしゃせいしょう)とは日本の美しい海岸の景色の表現です。
夏本番、海なし県の長野では、海への憧れがあるんです。
夏、海という単語だけでどこかソワソワしてきます。
今は高速道路が発達して日本海も大平洋も近くなりましたが、それまでは海へ行くのは夏の一大イベントです。
新潟県には信州の海と呼ばれる海水浴場もありました。なつかしい。
日本海の砂は黒いというイメージがあります。
こちらは、両側を松の緑に囲まれた熱く白い砂山です。

砂は白くその先には、広大な青い海、大平洋が広がります。
穏やかな波が押し寄せる海岸、海には誰もいません。
波だけが絶え間なく押し寄せていました。
ここは、静岡県御前崎市の浜岡砂丘、目の前に広がるのは遠州灘です。

浜岡砂丘は、天竜川から流出する土砂が沿岸潮流に乗り、「遠州の空っ風(からっかぜ)」と呼ばれる強い西風によって内陸へ運ばれてつくられたといわれています。
つまり諏訪湖から流れ出した天竜川が途中で土砂を集めて大平洋に流れ出て、強い西風に流されはるばる浜岡砂丘まで流れ着いたということですね。
白い砂たちの長い旅を思うと「信州からの長旅、お疲れさま」と言いたくなりました。
砂丘には暴風林と竹垣が設けられています。

遠州の空っ風があまりに強く、西風の風下に位置する畑が砂で埋没するのを防ぐため、海岸線に対し斜めに設けられています。
風を避けながら防風林手前に砂を堆積させて畑や集落を守る工夫のようです。
砂丘の先の松林には竹垣が設けて、強い西風による砂の移動を防いでいます。
遠くに見える白い建物は、現在運転休止中の浜岡原発です。

延々と続く砂浜には、演習の空っ風を電気に替える大きな風車が立ち並んでいます。

砂丘の砂は白くてサラサラしていて歩きづらいですね。
夏の夕暮れの海岸は、風と波の音だけが響いていました。

砂丘の入口に波の上に立つ子供のオブジェがありました。防風林の松が目に眩しく映ります。

防風林、砂山、遠州灘に背を向けて子供が波に乗ったオブジェがありました。

この子供の石像は、「波小僧」と呼ばれる妖怪です。

遠州灘で漁をしている漁師の網に妙な生き物が引っかかりました。
見慣れない生き物は海小僧でした。
漁師は殺そうとすると、「命を助けてくれたら、雨や嵐が近づいたらお知らせします」と命乞いをしたそうです。
それを聞いた漁師は、海小僧を海に返してあげました。
以来、西から海鳴りがすれば晴れ、東からであれば雨、遠い東からなら嵐と波小僧が天気を教えてくれるようになりました。

漁師は海鳴りにより天候を判断して安全に漁をすることができるようになったそうです。
遠州灘の海鳴りは波小僧の仕業といわれ、遠州七不思議の一つです。
静かに打ち寄せる穏やかな遠州灘です。海小僧の海鳴りは聞こえますか?明日の天気を教えてくれていますか?
海岸にはパームツリーが植えられて南国の海のような夕暮れでした。