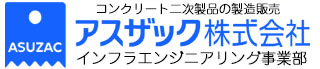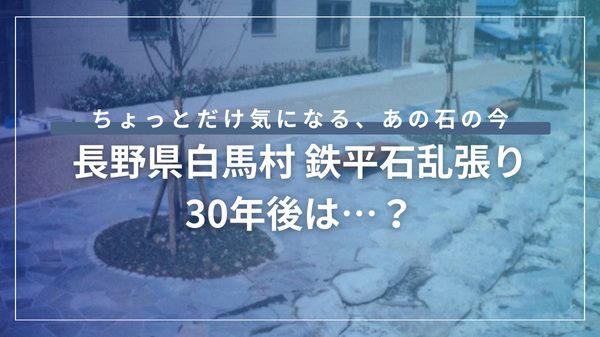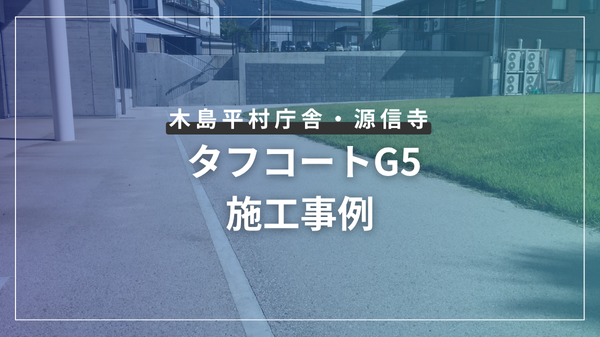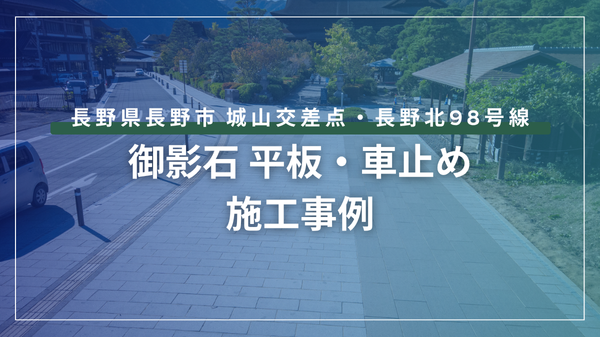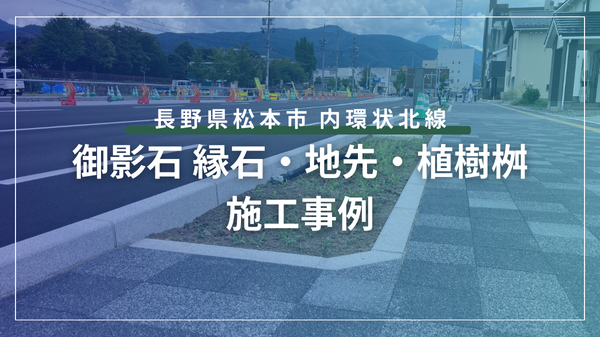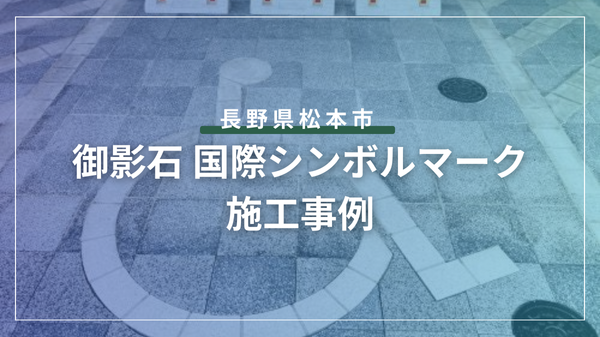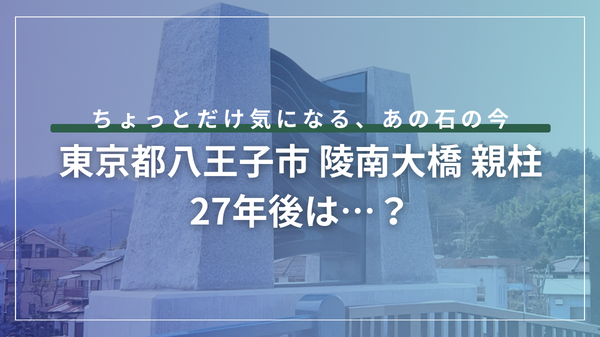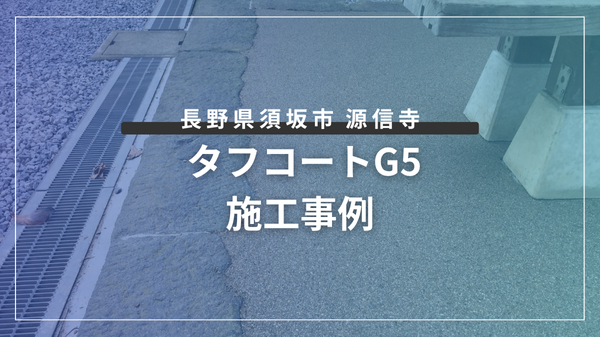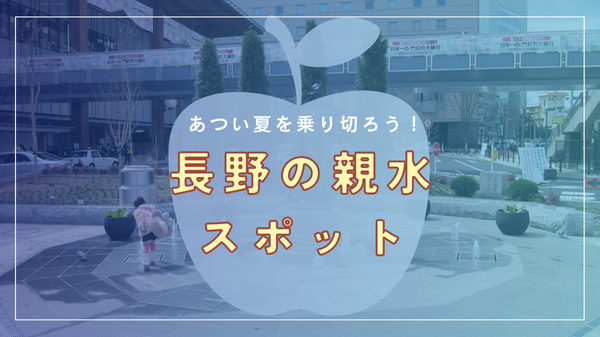有名人の学生時代の同級生が、現在どのような人生を歩んでいるのかを調査するテレビ番組が、かつて放送されていたのをご存知でしょうか。
主に一般の方を特集した番組でしたが、学生時代から現在に至るまでの人生の物語がとてもおもしろく、見始めるとつい最後まで見てしまうような内容でした。
この番組にヒントを得て、アスザックの石材チームでも『あの石 今どうしてる?』という企画が誕生しました。
過去に施工した石が、現在現場でどのように“過ごしている”のかを調査する特別企画です。
今後、不定期で調査結果をご紹介させていただきたいと思います。
今回は、白馬村で施工した鉄平石の現場です。
この鉄平石は、水環境整備事業として1994年に施工されたもので、小さな川の横の休憩スペースに鉄平石の乱形張りがされました。
施工からすでに31年もの年月が経過しているのですが、施工当時の写真がこちらです。
【施工当時の写真】


専門の職人さんの手により、情趣ある美しい景観に仕上がりました。
そして、31年経過した現在の様子がこちらになります。


細かくよく見てみると・・・




割れや剥がれもなく、健康で元気に過ごしていました!
冬は寒く、雪深い地域であるため、長い間とても厳しい環境にさらされていたことでしょう。
自然がつくり出した石ならではの強さを改めて感じました。




鉄平石とは、長野県の諏訪や佐久地方を主な産地とする安山岩の一種で、板状の節理により20~30mmほどの厚さに薄く剥がれる石材です。
耐火性や耐久性に優れているため、屋内外の壁や床など、さまざまな場所で使うことができます。
乱形張りにおいては、十字型の目地をつくってはいけないことや、石の形や大きさ、色合いをバランスよく配置することなど、細かな決まりごとがあります。
十字型の目地をつくると、石の弱点となる角を4箇所もつくってしまうことになり、破損の原因となります。
また、同じような形や色の石が集中して配置されていると、違和感が生まれ、美観を損ねてしまいます。
ただランダムに配置されているだけかのようですが、知識や経験を持つ職人さんにしかできない、とても難しい施工なのです。
『あの石今どうしてる?』という新たなテーマを掲げ、31年という長い年月から恐る恐る現場の調査に向かいましたが、変わらず現場で活躍し続けていることに大きな喜びを感じるとともに、誇らしく思いました。
やはり石の耐久性は格別です!
白馬村の鉄平石の現場からは以上です。
次回もご期待ください!